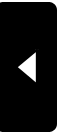2011年03月02日
最期の日
今日が最期の日になるかもしれない。
縁起でもないこというなよって
誰かに叱られてしまいそうだけれど、
本当にそういうことが起きてしまうのが
人生だから。
僕は今日を精一杯生きただろうか。
昨日までを精一杯生きてきただろうか。
ありがとうって、ごめんなさいって
素直に生きてきただろうか。
早朝4:30、看護士をしている母の緊急電話がなった。
友人の母が急死したんだー
僕はこの島で生き、
この島で最期の日を迎えたいと思っている。
17年前に死んだ同級生
7年前に死んだラグビー仲間。
昨年、往生した祖父。
僕は悲しくなんかない。
これっぽちも悲しくないかといえば嘘になるけれど、
彼らはきっとこの世界ではないところでも
必要とされている仲間だったんだと思うから。
ー
生きているひとだけの世の中じゃないよ。
生きている人の中に、死んだひとも一緒に生きているから、
人間はやさしい気持ちを持つことができるのよ、
灰谷健次郎の小説「太陽の子」より
縁起でもないこというなよって
誰かに叱られてしまいそうだけれど、
本当にそういうことが起きてしまうのが
人生だから。
僕は今日を精一杯生きただろうか。
昨日までを精一杯生きてきただろうか。
ありがとうって、ごめんなさいって
素直に生きてきただろうか。
早朝4:30、看護士をしている母の緊急電話がなった。
友人の母が急死したんだー
僕はこの島で生き、
この島で最期の日を迎えたいと思っている。
17年前に死んだ同級生
7年前に死んだラグビー仲間。
昨年、往生した祖父。
僕は悲しくなんかない。
これっぽちも悲しくないかといえば嘘になるけれど、
彼らはきっとこの世界ではないところでも
必要とされている仲間だったんだと思うから。
ー
生きているひとだけの世の中じゃないよ。
生きている人の中に、死んだひとも一緒に生きているから、
人間はやさしい気持ちを持つことができるのよ、
灰谷健次郎の小説「太陽の子」より
2011年02月18日
オーガニック石けんと「きのす」


昨日、ようやく甑島産のオーガニック石けんができました。種類は、ヨモギと島みかんの2種類。
お手手しっとり、こしき美人計画です!!!
次回は、甑島名産の椿油とツバキの花を用いて赤い石けんを試作予定!石けんづくりは、一回の制作におよそ一ヶ月の期間が必要となります。お酒やチーズなどと同じように石けんも熟成させていくんですね。販売開始は、8月を予定しています。それまで、手を洗わずに待っていてくださいね(笑)
また、今日は「きのす」を搾りました。きのすとは、甑島ならではの呼び方で、よくお正月等の縁起の良い日に使われる橙(だいだい)の果汁のことです。僕の住む地域では、刺身を食べる際に、お醤油にしぼって魚を食べたり、焼酎に垂らして呑むことがあります。大変酸味のある果物で、ゆずやレモン、カボスなどの仲間です。
きのすは、おそらく「木からとれる酢」のようなものだから・・・きのす。
昔、調味料の少なかった時代に、甑島では酢のかわりとしてきのすを身近な調味料(かくし味)として代々用いてきたのかもしれません。
だいだいだけに(笑)
この「きのす」に関しては、製造の申請や許可などをとってから、正式に販売していきますので、今しばらくお待ちくださいね。それまでに、色んなバリエーションを考えていきたいと思います。
2011年02月18日
島 米
まもなく甑島からはじまります。
全国の都市と農村をつなぐ「島米」プロジェクト
http://shimagome.jp/
一足先に、甑島のおいしい風景をつくる「ふるさとの米づくり」に取り組みます。
商品は、パックされたお米そのものではなく
米づくりとふるさとの風景や暮らし!!
只今「島米」サイト準備中!お気に入りやリンク先に登録して
オープンまでお待ちくださいね!
ヤマシタケンタ
全国の都市と農村をつなぐ「島米」プロジェクト
http://shimagome.jp/
一足先に、甑島のおいしい風景をつくる「ふるさとの米づくり」に取り組みます。
商品は、パックされたお米そのものではなく
米づくりとふるさとの風景や暮らし!!
只今「島米」サイト準備中!お気に入りやリンク先に登録して
オープンまでお待ちくださいね!
ヤマシタケンタ
2011年02月16日
未来にあるふつう
今にない、新しいものをつくる。ではなく
未来にある、ふつうのものをつくる。
appleとフェイスブックでインターンしていた上杉周作さんのことば。
それは、自分自身の甑島での生き方にも置き換えることが出来るんじゃないか。
未来って言うと、なんだかとてつもなく遠いことのような気がするよね。
ましてや、自分には関係のないことのような気さえする。
僕は今日、種まきをしたー
そのとき思ったんだ。
未来ってのは、ずっと遠くにあるものではなくて
「今」この瞬間ここにあるんだって。
一粒ひとつぶ、小さな種を蒔きながらそう思った。
僕には、この島を変えてやろうとか、変わらなきゃいけない!みたいな感情はない。
だけれど、今のままでいいとは思わない。僕にあるのは
この島をもっと「好きになりたい!」って思う気持ちなんだ。
田を耕すことも、島の風景のことも、ふるさとを好きになりたいと思うから。
好きになって欲しいから。
今にない、新しいことをする。ではなく
未来にある、ふつうの暮らしをつくるー
未来にある、ふつうのものをつくる。
appleとフェイスブックでインターンしていた上杉周作さんのことば。
それは、自分自身の甑島での生き方にも置き換えることが出来るんじゃないか。
未来って言うと、なんだかとてつもなく遠いことのような気がするよね。
ましてや、自分には関係のないことのような気さえする。
僕は今日、種まきをしたー
そのとき思ったんだ。
未来ってのは、ずっと遠くにあるものではなくて
「今」この瞬間ここにあるんだって。
一粒ひとつぶ、小さな種を蒔きながらそう思った。
僕には、この島を変えてやろうとか、変わらなきゃいけない!みたいな感情はない。
だけれど、今のままでいいとは思わない。僕にあるのは
この島をもっと「好きになりたい!」って思う気持ちなんだ。
田を耕すことも、島の風景のことも、ふるさとを好きになりたいと思うから。
好きになって欲しいから。
今にない、新しいことをする。ではなく
未来にある、ふつうの暮らしをつくるー
2011年02月12日
ケンタ
ケンタッキー・フライドチキン。
そう、略してケンチキ。
京都での学生時代、ケンチキ行こうよ!って、友達に言うと、???な顔をされた。その後のニックネームは、一時期ケンチキだった僕(笑)鹿児島じゃ、ケンチキっていうんだよ!!!って力説しても誰も信じてくれなかった笑い話。
ケンチキこと、ヤマシタケンタ、ではなく(笑)、創業者のカーネルサンダースのこと。
彼は、40才のときに、ガソリンスタンドの一角を借りて、6席だけでの小さなレストラン「サンダース・カフェ」をオープンさせました。
しかし、高速道路建設の影響を受けて65才の時に店を閉店してしまいました。
資産の殆どを失ったカーネルサンダースは、この逆境から世界初の「フランチャイズビジネス」を生み出しました。
フライドチキン片手に「フライドチキンの調理法を教えるから、かわりに売り上げの一部をくれ。」というものでした。
なんと、ことごとく1009社もの会社に断られました。しかし、彼はそれでも諦めませんでした。なんと、1010社目の会社訪問で契約をとり、ここから「ケンタッキー・フライドチキン」こと、ケンチキの歴史が始まったのでした。
と、自分に言い聞かせています(笑)
自分の信じられるものは、何か。自分にできることは、何か。それは、きっと足元に転がっているはずです。
そう、略してケンチキ。
京都での学生時代、ケンチキ行こうよ!って、友達に言うと、???な顔をされた。その後のニックネームは、一時期ケンチキだった僕(笑)鹿児島じゃ、ケンチキっていうんだよ!!!って力説しても誰も信じてくれなかった笑い話。
ケンチキこと、ヤマシタケンタ、ではなく(笑)、創業者のカーネルサンダースのこと。
彼は、40才のときに、ガソリンスタンドの一角を借りて、6席だけでの小さなレストラン「サンダース・カフェ」をオープンさせました。
しかし、高速道路建設の影響を受けて65才の時に店を閉店してしまいました。
資産の殆どを失ったカーネルサンダースは、この逆境から世界初の「フランチャイズビジネス」を生み出しました。
フライドチキン片手に「フライドチキンの調理法を教えるから、かわりに売り上げの一部をくれ。」というものでした。
なんと、ことごとく1009社もの会社に断られました。しかし、彼はそれでも諦めませんでした。なんと、1010社目の会社訪問で契約をとり、ここから「ケンタッキー・フライドチキン」こと、ケンチキの歴史が始まったのでした。
と、自分に言い聞かせています(笑)
自分の信じられるものは、何か。自分にできることは、何か。それは、きっと足元に転がっているはずです。
2011年02月01日
Hungry
甑島を離れた時に感じていた、疎外感みたいなものって、大人になればなるほど、出身者の多くが感じた経験あると思う。ましてや、会社の跡継ぎでも何でもないよ!ってひとなら尚更あると思う。以前の自分がそうだったように。
一般的に「ふつう」のひとには優しくない環境だよなって思う。ハローワークみたいなものだってないし、給料が安くて、仕事が少ないって、結構なハードルの高さだと思う。移住するにしても、知り合いがいるか、窓口がなきゃ不安だよね。
島で家族と一緒に暮らすのは、中学卒業までのせいぜい15年。本土で長く暮らしていると、島に帰る理由ってやつがさ、どんどん薄くなっていくし、それぞれの生活を大事にしなきゃならなくなる。ますます島にUターンするのが億劫になるのは、凄くわかる。
皇帝ナポレオンが言ってた。
戦地の状況?
状況とは、そこにあるものじゃない。
自分でつくるものだ、と。
島には仕事がない、仕事がないと、いつまで言い続けるんだろう。そろそろいいんじゃないかと思う。
僕がこどものころから、
ずっとそればかりだ。
もう、うんざり。
実際には、仕事がないんじゃない。仕事があってもそれを知らせる方法や窓口がないんだと思う。
島に住みたいと思うひとたちの不安を取り除く「何か」がしたいと思う、今日この頃。
小さな島のハローワーク。
小さな島の情報誌。
小さな島の不動産。
アイデアは、つきない。
お金はない(笑)
そのうち、入るさ。
なぜなら、入ると思っているから(笑)
しかし、尽きる。
アイデアとは違うね。アイデアを、カタチにしなきゃならないね。最近、物事に対してハングリーな自分を見失ってたから、お金がないぐらいがちょうどいい。
そう、言い聞かせる(笑)
最後の五百円で、
パンを買うか?
それとも釣り道具を買うか、だな。
アイムハングリー!
一般的に「ふつう」のひとには優しくない環境だよなって思う。ハローワークみたいなものだってないし、給料が安くて、仕事が少ないって、結構なハードルの高さだと思う。移住するにしても、知り合いがいるか、窓口がなきゃ不安だよね。
島で家族と一緒に暮らすのは、中学卒業までのせいぜい15年。本土で長く暮らしていると、島に帰る理由ってやつがさ、どんどん薄くなっていくし、それぞれの生活を大事にしなきゃならなくなる。ますます島にUターンするのが億劫になるのは、凄くわかる。
皇帝ナポレオンが言ってた。
戦地の状況?
状況とは、そこにあるものじゃない。
自分でつくるものだ、と。
島には仕事がない、仕事がないと、いつまで言い続けるんだろう。そろそろいいんじゃないかと思う。
僕がこどものころから、
ずっとそればかりだ。
もう、うんざり。
実際には、仕事がないんじゃない。仕事があってもそれを知らせる方法や窓口がないんだと思う。
島に住みたいと思うひとたちの不安を取り除く「何か」がしたいと思う、今日この頃。
小さな島のハローワーク。
小さな島の情報誌。
小さな島の不動産。
アイデアは、つきない。
お金はない(笑)
そのうち、入るさ。
なぜなら、入ると思っているから(笑)
しかし、尽きる。
アイデアとは違うね。アイデアを、カタチにしなきゃならないね。最近、物事に対してハングリーな自分を見失ってたから、お金がないぐらいがちょうどいい。
そう、言い聞かせる(笑)
最後の五百円で、
パンを買うか?
それとも釣り道具を買うか、だな。
アイムハングリー!
2011年01月31日
こどもの頃に見た風景が
ずっと心の中に残ることがある。
いつか大人になり、
さまざまな人生の岐路に立った時、
ひとの言葉でなく、
いつか見た風景に励まされたり、
勇気を与えられたりすることが
きっとあるような気がするー
写真家 星野道夫
ずっと心の中に残ることがある。
いつか大人になり、
さまざまな人生の岐路に立った時、
ひとの言葉でなく、
いつか見た風景に励まされたり、
勇気を与えられたりすることが
きっとあるような気がするー
写真家 星野道夫
2011年01月23日
種をまくシゴト
里の八幡神社から、太鼓を打つ音が鳴り響いている。
神主見習いのトモさんだ。
山の方から、田を打つ耕運機の音が聞こえてくる。
武家屋敷の石笛案内人ことマサキヨおじさんだ。
スピードをあげて沖へ向かう漁船のエンジン音が鳴り響いている。
さっき港ですれ違った漁師かもしれない。
道に並んで手を合わす、葬儀の参列者たち。
島のばあちゃんが亡くなった。
鳥のさえずり、森が風に揺れる。
風はまだ、冷たい。
そのどれもが美しくて、僕はただ茫然と言葉を失い、
水田の前に立ち尽くしている。
この島に生きるということ、すなわちこの島に死ぬということ。
自分が、この島でどういう死を迎えるのか、
いつも考えさせてくれる島びとたちの死。
いま、あるものすべて。
なんでもない日常が、
たまらなく特別な風景に思えてくることがある。
みんな生きている。
それぞれの人生を生きているんだよね。
ただ、それだけで大したもんだと僕は思うよ。
誰ひとりとして、同じ人生を歩んではいないのだから。
みんな、自分だけの物語を生きる主人公なんだと思う。
農夫たちは、なぜタネを蒔くのか。
それは、収穫という希望があるからだという。
僕は、なぜこの島に生きるのか。
生きようとしているのか。
たぶん、ここに希望があるからなんだと思う。
希望をみたいと、思うからなんだと思う。
種をまくひと。
希望の種をまくひと。
そんなひとになりたいな。
神主見習いのトモさんだ。
山の方から、田を打つ耕運機の音が聞こえてくる。
武家屋敷の石笛案内人ことマサキヨおじさんだ。
スピードをあげて沖へ向かう漁船のエンジン音が鳴り響いている。
さっき港ですれ違った漁師かもしれない。
道に並んで手を合わす、葬儀の参列者たち。
島のばあちゃんが亡くなった。
鳥のさえずり、森が風に揺れる。
風はまだ、冷たい。
そのどれもが美しくて、僕はただ茫然と言葉を失い、
水田の前に立ち尽くしている。
この島に生きるということ、すなわちこの島に死ぬということ。
自分が、この島でどういう死を迎えるのか、
いつも考えさせてくれる島びとたちの死。
いま、あるものすべて。
なんでもない日常が、
たまらなく特別な風景に思えてくることがある。
みんな生きている。
それぞれの人生を生きているんだよね。
ただ、それだけで大したもんだと僕は思うよ。
誰ひとりとして、同じ人生を歩んではいないのだから。
みんな、自分だけの物語を生きる主人公なんだと思う。
農夫たちは、なぜタネを蒔くのか。
それは、収穫という希望があるからだという。
僕は、なぜこの島に生きるのか。
生きようとしているのか。
たぶん、ここに希望があるからなんだと思う。
希望をみたいと、思うからなんだと思う。
種をまくひと。
希望の種をまくひと。
そんなひとになりたいな。
2011年01月06日
2011年のいま
私の仕事始めは、4日でした。
当たり前のことかもしれないですが、休むって大事なことですね(笑)
何を今更!と思われるかもしれませんが、フリーランスで仕事をしていると、いつが仕事の時間で、いつが休みなのか分からなくなるのです。
もちろん、今のところ従業員はいないので、すべてにおいて采配権を握っているのは、私です。自分で、自分をコントロールして、マネジメントもします。時折、プライベートと、そうでないこととの境が分からなくなります。
そういったことなどから、普段からなんとなく社長の気分だけは味あわせていただいております(笑)こればっかりは、ならなきゃ分からないコトですからほんとに、気分だけです。
但し、なったように振舞え、です。
新年の抱負みたいなのは、なんだか、新年だから、ということで無理やり言わされてるみたいであまり好きじゃないんですが、「今」という時間が、自分にとってどういった時間であるのかを知る必要があるとおもいました。或いは、それを決める必要がありました。
2011年と2012年の2年間は、
知識と人脈と資本を得ることに取り組み、自己への投資を大切にします。
そして2013年の12月、
まず、独立開業します。
これが、わたしなりの抱負です。誰かに必要とされる知識を得ること、誰かに必要とされる人間になること、誰かの信頼を積み重ねていくこと、すなわちファンをつくること、そして、自分の夢をカタチにするために必要なものを備えていくこと。
その「誰か」を目の前のたいせつなひとに当てはめていくと、より具体的になりました。
以前のわたしなら、
全てのひとを指して、誰にも負けない知識量を持つこと、誰よりもたくさんの知り合いを持つこと、少しでも多くのお金を貯めること!だ、なんて言っていたかもしれません。
自分が、会社が、成長していく上で、それらは決して無意味ではないと思いますが、常に戦う相手が存在するというのは疲れます。それに、戦い続けないといつか負けてしまいます。
私は、負けない経営がしたい。
勝ちと負けというような比較の対象ではなく、負けという概念そのものをなくした「負けのない」もの。それが、価値(勝ち)なんじゃないかと、私は思うのです。
資本に対する考えも、以前、カラダを壊して入院したときに感じました。甑島に帰り、農作業で腰を痛めてわかりました。うまく行かないカラダの苦しみのおかげでわかりました。
資本とは、お金のこともですが、資本を得続けるための何か、であることなんだと気がつくことができました。ですから、自分自身のカラダもそれであると思うんです。
開業することが、ゴールではないのですから、そのあとに続くための資本です。
早速、フェリーに乗って腰の検査に本土へ渡ります。思い立ったら吉日です。これも、自己投資のひとつなんだと思えるようになりました。
おととい(笑)
今が、自分にとってどういった時間であるのかを知ること、考えること、決めることは、将来の自分を築いていく大切なことなんだなと思うことができました。
それが、あるとないとでは2013年の12月を迎えるとき、支えてくれる人々への感謝の深さが違ってくるように思いました。
2011年、
今年もどうぞ宜しくお願い致します。
当たり前のことかもしれないですが、休むって大事なことですね(笑)
何を今更!と思われるかもしれませんが、フリーランスで仕事をしていると、いつが仕事の時間で、いつが休みなのか分からなくなるのです。
もちろん、今のところ従業員はいないので、すべてにおいて采配権を握っているのは、私です。自分で、自分をコントロールして、マネジメントもします。時折、プライベートと、そうでないこととの境が分からなくなります。
そういったことなどから、普段からなんとなく社長の気分だけは味あわせていただいております(笑)こればっかりは、ならなきゃ分からないコトですからほんとに、気分だけです。
但し、なったように振舞え、です。
新年の抱負みたいなのは、なんだか、新年だから、ということで無理やり言わされてるみたいであまり好きじゃないんですが、「今」という時間が、自分にとってどういった時間であるのかを知る必要があるとおもいました。或いは、それを決める必要がありました。
2011年と2012年の2年間は、
知識と人脈と資本を得ることに取り組み、自己への投資を大切にします。
そして2013年の12月、
まず、独立開業します。
これが、わたしなりの抱負です。誰かに必要とされる知識を得ること、誰かに必要とされる人間になること、誰かの信頼を積み重ねていくこと、すなわちファンをつくること、そして、自分の夢をカタチにするために必要なものを備えていくこと。
その「誰か」を目の前のたいせつなひとに当てはめていくと、より具体的になりました。
以前のわたしなら、
全てのひとを指して、誰にも負けない知識量を持つこと、誰よりもたくさんの知り合いを持つこと、少しでも多くのお金を貯めること!だ、なんて言っていたかもしれません。
自分が、会社が、成長していく上で、それらは決して無意味ではないと思いますが、常に戦う相手が存在するというのは疲れます。それに、戦い続けないといつか負けてしまいます。
私は、負けない経営がしたい。
勝ちと負けというような比較の対象ではなく、負けという概念そのものをなくした「負けのない」もの。それが、価値(勝ち)なんじゃないかと、私は思うのです。
資本に対する考えも、以前、カラダを壊して入院したときに感じました。甑島に帰り、農作業で腰を痛めてわかりました。うまく行かないカラダの苦しみのおかげでわかりました。
資本とは、お金のこともですが、資本を得続けるための何か、であることなんだと気がつくことができました。ですから、自分自身のカラダもそれであると思うんです。
開業することが、ゴールではないのですから、そのあとに続くための資本です。
早速、フェリーに乗って腰の検査に本土へ渡ります。思い立ったら吉日です。これも、自己投資のひとつなんだと思えるようになりました。
おととい(笑)
今が、自分にとってどういった時間であるのかを知ること、考えること、決めることは、将来の自分を築いていく大切なことなんだなと思うことができました。
それが、あるとないとでは2013年の12月を迎えるとき、支えてくれる人々への感謝の深さが違ってくるように思いました。
2011年、
今年もどうぞ宜しくお願い致します。
2010年12月30日
何を、残すか

先日、椎茸の収穫作業をするということを聞き、いきたい!と、即答してとなり町までお邪魔してきました。
最近のスーパーにある、ほとんどの椎茸が中国産、もしくは椎の木ではない木で栽培されたもの、或いは原木での栽培ではないものになっています。
ですから、皆さんが多く口にしている椎茸は、実は、椎の木のシイタケではないのです。
そんななか、椎の木でつくる椎茸だけにこだわってつくるご夫妻が甑島にはいます。
椎の木からでてきたシイタケをはじめて見たとき、スーパーに並ぶそれとは色もカタチも違うものであるということが、すぐにわかりました。味や、風味も、これまで食べたどのシイタケよりも優れたものでした。
収穫されたのち、乾燥されて、袋詰めされ、今も、ひと知れずコツコツと出荷されています。
この島のみらいを考えるとき、
委員会もいいと思う。協議会もいいと思う。組合も、NPOも、組織化だって。
だけど、僕は思います。
最後に行き着くのは、甑島を純粋な気持ちで心から想うひと、楽しむひとでしかないということ。そして、残っていくものは人間の思想と環境。
まずは、自分が仕事を、やるべきことを楽しむこと。仕事を楽しむひとは、人生を愉しんでいるから。僕は、シイタケのことはわからないけれど、ミノタケは分かりながら成長していきたいと思います。
うまい!
椎の木のシイタケのことです(笑)
2010年12月29日
年の瀬のモチ

いよいよ、今年も残すところあとわずかとなりました。最近の僕はというと、農業倉庫と自宅、アートプロジェクトの事務所、山下商店の事務所と、掃除するところが多く、まだまだ正月はやってこない感じです(笑)。
先日は、夏に収穫したヒヨクモチを使っての餅つきがあり、2日間に渡って親戚のお姉様方が愛を込めて丸めていました。

こうして、小さかったいのちの種がおもちになるまでのプロセスをみることができて、生産者として幸せなことだとおもいました。
そう、
あとは食べる、幸せのみ!!(笑)ということで、正月太りしないように気をつけます。
2010年12月24日
新しい世界

自分だけの世界から抜け出して、多くの出会いを求めてみると、等身大の自分がわかる。
素直に、謙虚に、柔軟に
これまで知らなかった人たちと出会うと見えてくる新しい考えかた、生きかた、価値観、知らなかった自分。やがて、それらがまた、新しい自分の世界をつくる。
僕は、やっぱり出会いに敏感な人間でいたいと思います。名刺の交換だけに満足していても何も生まれないし、何も始まらない。
大切なことは、
いつだって出会いの先にあると思う。
何でもないような、意味のない出会いなんてどこにもない。
これから、フェリーに乗って甑島に帰ります。もちろん、
新しい出会いに期待しながら、
2010年12月20日
幸せの条件

どんなに島が経済的に潤ったとしても、この地域に住むひとびとが、本来の自分の姿で生きていなければ、島の心が永遠に満たされることはない。
島の暮らしは豊かになったというけれど、あれから本当に幸せな日々を送ってきたのか。島の現状をみていて、僕はまだ分からないでいる。
ジッタクイ
島にはジッタクイがあった。ジッタクイとは、方言で、雨の日になるとぬかるんでしまう道や水溜まりのこと。
今のこどもたちは、ジッタクイの方言の意味を知らないという島のおじさんがいた。親が方言を話さないからだ、と。
僕は、それだけじゃないと思った。
島の道は舗装されて、ジッタクイそのものがなくなったからだと思った。
産業構造の四割以上を土建業に関わるひとたちが占めている甑島。もしかすると、島はそんな経済の奴隷になっているんじゃないかって思うと、とても哀しくなった。
また、地域の文化は、地域産業・経済と確かに繋がっているんだと実感した小さな瞬間でもあった。
僕らに残されてきたもの、残されなかったもの。それらを感じ取り、この島のこどもたちに僕らが、今度は何を残すか、なにをつくるのか。変革の時は、近づいている。
それは、冬のど真ん中にいるときにも、静かに春の気配が近づいているように。甑島の夜明けが、もうそこまでやってきている。
島に生きる幸せの条件を満たすためには、なにが必要なのか、もう一度考えてみたい。この島に誇りを抱き、夢をみて帰ってくるのだろうか。僕らは、帰ってきたときに、受け入れる準備はしているだろうか。
観光や、新産業、ここに生きていく島のひとたちがしあわせに生きるための活動でなきゃ、どんな仕事も、どんな政策も、プロジェクトも意味がない。
大学の教授や、地域興しで有名な方の講演や、指導、ワークショップなど、いろいろあるけど、本当は、自分たちがその主役であることに気が付けなければ何度やっても意味がないと僕は思ってる。
島に幸せに生きる条件って、地域社会と向き合いながら、自分を幸せにしていく条件のことかもしれないね。
※写真は、こしきアートプロジェクトの地元スタッフの美鈴さん。美鈴さんは、郵便局に勤めながら、島のパティシエとして腕を磨いています。
2010年12月18日
選ぶとは、選ばない

早いもので、今年もあと僅かになりましたね。最近の僕はというと、時間を作って、この一年間を振り返りながら事務所の整理をしています。
この整理というのは、掃除とは違い、ただモノを捨てたり、並べたりするのではなく、意識的に来年の計画を実現していくための事務所づくりの整理のことです。
今日は、これまで集めてきた日本各地のサンプル商品と、自分の商品をあえてとなり同士に並べてみました。

この一年間、自分のやってきたことと、動きだそうとしていることが、目指すべき場所から離れていないか、間違っていないか、ズレていないか。自分のような商品たちを眺めながら、自分に問いかけています。
次にしなければならないことは、目の前に、身の周りにあるものです。それをうやむやにしていたら、遠い未来は、いつまで経っても遠いまま。
選ぶとは、
選ばないという選択も含んでいます。
捨てるとは、
捨てないという選択も含んでいます。
僕は、この島に生きるという選択肢を選びました。島に帰ってきて思うのは、生きるっていうのは、島に住むっていうこととは少しだけニュアンスが違うことなんじゃないかなって。
それは、そこにあるものではなくて、自分の内側から生まれてくる感情であり、本物の自分と出会う旅みたいなことなんじゃないかって。
島に生きるというのは、実のところ、誰でもない「自分」自身を生きるということであり、自分の内なる声と、そして、支えてくれる仲間たちを大切にできる自分であることなんじゃないかって。
毎日毎日、少しの軌道修正をしながら、新しい日々をやり直し続けたいと思います。
2010年12月16日
黒い使者

あした、フランスからの黒い使者が甑島のお店に並ぶのか、それとも並ばないのか。
ブラックラディッシュは、甑島の黒船となるのか。それとも、ニワトリのえさになるのか。
大根は、白い!という概念を覆してしまうこの黒さ。味は、保証しません。いやいや、頼むから保証してくれよというあなた!
正解です(笑)
いつもと違う大根を食べたいというかた、珍しもの好きなあなた。万が一、お店に並んだ場合は、お買い求めください。
Posted by ヤマシタケンタ at
11:56
│Comments(2)
2010年12月13日
よもぎの石鹸

先週の日曜日、よもぎ石けんを試作し、型に流し込んでいたものを取り出してカットしました。
乾燥させたよもぎを、オリーブオイルや、ココナッツオイルなどをミックスしたオイルに混ぜ合わせてエキスを抽出させていました。朝から、ほんのりよもぎの香りが漂っています。
これから、あと3週間ほど熟成させてゆっくり乾燥させていきます。次は、島ミカンの皮や椿オイルを利用したものにチャレンジする予定です。
どんどん種類を増やして、4月頃からの販売を目処にやっていこうと思っていますので、お楽しみに。
2010年12月07日
ゼロダテ
先日の誕生日にいただいた農村Tシャツについて。秋田県zero dateのスタッフブログで紹介されました。
http://www.zero-date.org/staffblog/2010/12/t.html
http://www.zero-date.org/staffblog/2010/12/t.html
2010年12月06日
誕生日

昨日は、誕生日でした。
連日連夜の祝い事などで、胃と肝臓の調子が悪いです。午前4時、午前2時、午前4時、午後11時、しばらくは飲みたくないです。
誕生日のケーキをいただきました。みなさま、大変美味しかったです。それから、秋田出身のアーティスト藤林さんからもスペシャルなプレゼントが朝イチで送られてきました。秋田名産のジュンサイといぶりがっこ、そして、「農村Tシャツ」。
農村の後継者不足にちなんで、
No son.
息子がいない農村、ってことでシャレたものをいただきました。これからビシバシ愛用して、甑島の少子化対策に努めていこうと思います(笑)。
ようやく25歳になりました。いま、大学の頃に考えていたことをカタチにしている途中です。
5年後の30歳になるときは、いま、甑島で考えていることをカタチにしている途中だと思います。
僕らは、いつだって今という時間しか生きることはできない。過去に戻ることも、未来へのタイムマシンに乗ることもできないのだから。やっぱり、今を生きるより他にない。
今、目の前にあるものを大切にできる自分でいたいと思います。未来は、向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに(笑)
いえいえ、未来は、今この瞬間、ここにあります。今の自分は、5年前の自分が向かわせたのであり、それは過程に似た結果のようなものなんだと思う。
思考と感覚を巡らせ、軌道修正の連続。
その絶え間ない毎日が、30歳の僕を作るんだと思う。自分自身への挑戦です。
こどもたちに憧れを抱いてもらえるような、格好いい島の大人になること、島と、島に生きる人びとを輝かせていくこと。それが、自分自身に課せた最大のミッションです。
2010年12月04日
オーミンツーグーサマ
上甑島里町のスーパーから、たくさんの焼酎が消えてしまうことでしょう。
本日は、年に一度のエビスまつりの日なんです。
早速、大漁祈願の漁船パレードが行われました。恵比寿神社の下をグルグルと回ります。
昔から、この日は、一段と島の漁師たちが格好よく見えたものです。
保育園のこどもたちが、港にあつまっていました。みんな、目をキラキラさせながら、目の前を通る漁船の群れに手を振っていたのがとても印象的でした。
海の上のそれぞれの船には、その船の跡取りや孫たちが乗り込んでいます。とある船では、島の中学生が勇壮に舵をとっていました。本当に、たくましい存在で、僕の誇りでもあります。
きっとこの日に感じることの、意味の全ては、今はまだ分からないかもしれないけれど、これから島を離れて暮らし始めた頃、あるいは、大きな壁にぶつかってしまったとき、悩んでしまうとき、この日の何かがきっと、彼らの胸をあつくしてくれるんだと思います。
いつまでも、いつまでも、
この島に竜宮さまがいてくれることを、僕は祈っています。
本日は、年に一度のエビスまつりの日なんです。
早速、大漁祈願の漁船パレードが行われました。恵比寿神社の下をグルグルと回ります。
昔から、この日は、一段と島の漁師たちが格好よく見えたものです。
保育園のこどもたちが、港にあつまっていました。みんな、目をキラキラさせながら、目の前を通る漁船の群れに手を振っていたのがとても印象的でした。
海の上のそれぞれの船には、その船の跡取りや孫たちが乗り込んでいます。とある船では、島の中学生が勇壮に舵をとっていました。本当に、たくましい存在で、僕の誇りでもあります。
きっとこの日に感じることの、意味の全ては、今はまだ分からないかもしれないけれど、これから島を離れて暮らし始めた頃、あるいは、大きな壁にぶつかってしまったとき、悩んでしまうとき、この日の何かがきっと、彼らの胸をあつくしてくれるんだと思います。
いつまでも、いつまでも、
この島に竜宮さまがいてくれることを、僕は祈っています。
2010年11月30日
神様より仲間

お客様は、神様です。
僕は、本当は違うんじゃないかと思っています。そんなこと言うと、営業マンか誰かに叱られるかもしれませんね。
僕はほとんど、営業らしきことも告知もしません。するとしてもダイレクトにチラシを渡したり、話しをしたり。消費者にだけでなく、生産者側にも顔が見えるようなやり取りを心がけています。そして、お米を買って下さる方には僕の考えや想いはなるべく話そうとしています。
それは、買うという行為によって、農業や故郷が、消費して(されて)しまわないように。消費者は、ただお金を支払って食べて、終わり、ではないと消費者でもある僕自身が思っているからです。
そして、一百姓として苦労したことで感じたことは、お米の代金にはお米ができるまでの過程の物語も含まれているということ。
だから、お米を買うということは、「米づくり」を買うということだと思っています。
若者もいない。離島である。極端に平地の少ないこの甑島で、米づくりをするということ自体、無謀なことかもしれません。ましてや、農業の大型化や、農地の集約化を必要とする現在の日本農業のスタイルでは、甑島で農業を続けていくのは限りなく不可能に近いです。
この島の後継者が、全くといっていい程育っていない現状をみれば、それは明らだと思います。そういうこともあってか、やっぱり僕にとってお客様は、神様ではないんだと思います。
美しい故郷の姿を、ずっとずっと後世に残していきたい。この島に生きる人びとを輝かせていきたい。人と行為とお金の関係をリノベート(再構築)していきたい。それをさらに、カタチや仕組みとしてつくりだしていこうと動き始めています。
3月、どうぞお楽しみに!



![[私はKOSHIKI ART PROJECTを応援します。]](http://img01.chesuto.jp/usr/koshikiart/koshiki-art-project-2009_blogparts_006.jpg)