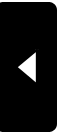2010年11月26日
する、しないこと
 ようやく秋の収穫期を終えて、ひと段落がつきました。島はすっかり冬模様で。毎日ビュービューと風が島を渡って行きます。
ようやく秋の収穫期を終えて、ひと段落がつきました。島はすっかり冬模様で。毎日ビュービューと風が島を渡って行きます。さて、そんななか…半年も前に大の釣り好きな先輩から食事の誘いを受けていたのですが、ちょうど慌ただしく走り回っていたアートプロジェクトの開催前だったために、お断りしていたこともあって…先日、ようやく遊びに行くことができました。
お宅について早々、予定通り(笑)釣りの話に花が咲きました。
なにを隠そう、わたくしヤマシタケンタ。この島に生まれ、海に囲まれて暮らす毎日のなかでの、しないことランキングを発表致します。
(効果音は、各自で御願いします)
第3位 自分(しごと)の安売り
第2位 偉そうな人にゴマスリ
そして、第1位が…なんと
釣りなんです(笑)。
周りは釣り釣り釣り釣りなんですが、僕は、どうしても潜る方が専門なんですね。以前は12月の日本海(福井)なども潜っていたほど。ただ、時期が時期なだけに、浮上する際に藻が首に掛かって一度だけ溺れました(笑)
そんな感じで、しないことランキング1位に釣りがくるわたしですが、釣り好きの先輩方が好きなんですね。
なんかこう、ひとが輝いてる瞬間?ワクワクしてるとき?イキイキしてるところ?に居合わせることができて、自分も幸せという感じなんですよね。
ですからまた、遊びに行こうと思っています。もちろんダメと言われても行きますから、美味しい魚を食卓に並べていただけたら…(笑)
話はズレますが、
近ごろ何らかの事業をやる身になって思うことは、会社として、個人事業主としても、やることを決めることより、やらないことを決めるということは難しいということ。
僕は、やりたいこと(実現したいこと)は割と多い方だと思うんですが、何でもやります!というようなタイプではないので、自分でもそのあたりの線引きが実に難しい。自分なりに守らなきゃいけないこともあるし、地域のルールみたいなものもありますから、周りとの兼ね合いとか考え出すと、もうキリがないくらい。
僕がこの島にしごとを作っていく上で、いまのところ「島米」や「新鮮野菜」という農産物をメインに活動しているけれど、どうしても甑島という地域のブランド品としては魚介類の取り扱いが必要不可欠になってくると思っているし、甑島という地域はやっぱり海のまちだとも思う。
そんな中、僕のつくる農産物は日常のありふれた風景でありながら、それら魚介類の引き立て役でもありたいと考えてきた。
そこで、今回「甑島のこだわり朝食セット」を限定販売させてもらうことに至り、すでに秋期分は完売したところです。
甑島で、埋もれている本物の商品を選りすぐってきちんと評価する。商品そのものの評価もだけれど、生産者や手作業での加工者・職人に対する評価まできちんと。
頑張っているひとが大勢いる分野で、僕があれこれ始めるよりも、その彼らを別な分野の視点から見ることで輝いてもらうこと。喜んでもらうこと。そして、それを機に島が少しでも良くなっていくこと。
ここに生きるひとたちが、互いに違う立場だからこそ面白いし、それぞれが違うことに意味があるのだと思う。その「違い」そのものはこの島の魅力であるし、それを活かすより他にない気もするのだ。
何より、甑島の資源は豊富な自然環境と思われがちだけど、そこに誇りを持ってイキイキと暮らしている村人たちの方が、ステキなんじゃないかと僕は思うのでした。
そういうわけで?(笑)
僕が釣りをする日は、まだ先のことかなのか?いやはや、釣りの面白さを分からせていただけるのか、今後の島暮らしにも乞うご期待下さい(笑)
2010年11月21日
こしき足袋コレ
 最近、地下足袋を履くひとが少なくなってきた日本ですが、こんな時代でも
最近、地下足袋を履くひとが少なくなってきた日本ですが、こんな時代でも山下商店は「これからも、ずっと、地下足袋と」※CM風に(笑)
仕事中、通りがかりの人によく「けぇんたくん、あぁんたはほんとに地下たぁびがー似合うねぇー。」って言われるのは、結構嬉しいこと。
地下足袋履いてない日は「今日は休み?」だなんて言われるほど、ほぼ毎日履いてます。
そんな時、学生時代の課題(卒業制作)を思い出します。
僕は、建築系の学科を専攻していて、建築(ハード)だけでは地域デザインはできないという話がしたくて…
例えば、「山下商店とユニクロとのコラボでこれからの農作業を格好良くしていきます」的な話しを大勢の教授と学生たちの前でプレゼンテーションをしたとき、山下商店が架空の設定だった上に、実在するユニクロのインパクトが強すぎて、伝えたかったことがうまく伝えられなかったというか…
実際に、ユニクロと農作業ファッションを組み合わせて地下足袋スタイルでプレゼンテーションしたもんだから、必要以上にうまく伝わってしまうという苦い思い出。
ユニクロの関係者様!どうか、わたしにチャンスを(笑)
地下足袋を履きこなし、ユニクロ×農作業スタイルをこよなく愛する甑島のじいちゃん・ばあちゃん・若者と子どもたち特集を是非とも!
既成概念に捕らわれず、農業?仕事?ライフスタイル?島暮らし?を通じて甑島を楽しく・格好良く、そして元気にしていきたい今日この頃。
いや、前からか。
これまでも、これからも、少しずつだけれど「夢は叶う」を体現していける大人でいようと思います。
2010年11月14日
あれから1年
 今日で、甑島にUターンしてからちょうど1年になりますが、本当にあっという間でした。
今日で、甑島にUターンしてからちょうど1年になりますが、本当にあっという間でした。この1年は、自分自身が他との関わり合いの中で埋もれていかないための努力と、これから歩んでいく方向を模索し続けること・考え続け・磨き上げていこうとしていました。
何度も折れそうでしたが(笑)
それでも、やっぱり続けてこれたのは甑島の若者たちを始め、世界各地にいる多くの仲間と協力者たちに恵まれたことが、僕の最大の財産であり、それこそが僕のすべてと言っても過言ではないような気がしています。
改めて、背中を押してくれた・押してくれている仲間たち、ありがとう。
しかしながら、最後に決断し、判断していくのはやっぱり自分です。切り拓いていく第一歩目は、自分の足以外にありません。
僕は12月1日より、次のステップに移ろうと思います。里町のとある施設内に「山下商店」Design studio & Officeを開設いたします。皆さん、今後もどうぞご支援をよろしくお願いいたします。
2010年11月12日
上甑島の家 発売
 続いて、今日から里港と甑島館の売店にて発売になりました。
続いて、今日から里港と甑島館の売店にて発売になりました。甑島の家シリーズ第1弾は、里町にあるお宅(薗上地区・上町)がモデルとなりました。
甑島の地形は、南北に長く起伏に富んでいます。また、文化や習慣などの違い・自然環境との関わり方などから、独自の住宅建築が発達してきました。
―
女「はがき、ご丁寧にありがとうね。はがきだなんて、あなたってす・て・きっ!」
男「へへへっ、どういたしまして。」
女「ねぇ、甑島楽しかったぁ?」
男「うん!もう、最高なところだったぜ!」
女「えっなによ、最高ってどういうこと!?一体どんなとこだったっていうのよ!」
男「はははっ…それはヒミツなんだ。」
女「えーー、やだやだー!絶対やだぁー!なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでぇーーー!?」
男「それは…
組み立ててからのお楽しみさ。」(笑)
なんつって!
女「わぁ、ステキなおうち」
…
男「きみのほうがステキさ」
なんつって(笑)
2010年11月09日
世間遺産シリーズ発売
 世界遺産ではありません(笑)
世界遺産ではありません(笑)ついに、明日から甑島館と里港売店にて世間遺産シリーズ(ポストカード)の発売です。
もちろん、お声を掛けていただけたら島内(上/中)配達いたしますよ。
1枚180円※ちゃんとPR
「世間遺産」とは、読んで字のごとく…古くから甑島地域に残されてきたものや、これからも残していきたい財産・ステキな風景、島のくらしなどのことを世間遺産と呼んでいます。
過去に地域が失ってしまったものも含めて、この1枚のポストカードをきっかけに、もう一度この島を見つめ直していく機会をつくること、また、島を訪れた人たちには故郷の原風景を懐かしんでいただきたいというような想いで作りました。
僕が生まれて約25年という短い月日の中でも、故郷は良くも悪くも大きく変貌しました。
島を離れて、それを目の当たりにしたとき、ありふれた島の日常は、誰かの非日常であり、特別な毎日であることを自分自身が再認識したことをきっかけに、世界遺産ではなくても、地域のみんなに愛されて大切にされていく故郷をつくりたい。そして、それらを愛し、誇りに想えるような自分でいよう。と以前感じていたことから今回のポストカード制作に至りました。
ちなみに、今のところ僕が甑島の世間遺産を勝手に認定しています。悪しからずご了承下さい(笑)
次回は、お隣の上甑町の世間遺産シリーズ発売を検討中です。内容は、まだヒミツ!ひとまず明日の発売をお楽しみに。
では、ちょっと暗くなりましたが、これからまた畑に行ってきます。あー、寒い!!
2010年11月07日
文化の火を
 今日は、里町の文化祭の日で、朝8時から恒例の水産加工品・農産物の朝市がありました。
今日は、里町の文化祭の日で、朝8時から恒例の水産加工品・農産物の朝市がありました。僕も島の方に声を掛けていただき、半ば強制的に(笑)参加を勧められて、島米を出すことにいたしました。
声をかけていただけるということは、本当に有り難いことです。
島米(コシヒカリ・ひのひかり)とオリジナル絵葉書、手づくりのオーガニック石けん(レモングラス)の出品になりました。
売れ行きがどうこうより(もちろん売れました)、僕は殆ど営業や宣伝も最低限のことしかしないので、まずは少しでも多くのひとに「けんたくん、お米作ってるんだね!」「いつも売ってるの?」「連絡先を教えて。」という具合に島米のことを知ってもらえることができ、来年・再来年の米づくりに向けて大変良い機会になりました。
文化祭の方はというと、
今年は、里町が何年かに一度の薩摩川内市のなんとかフェスティバル(忘れた)の担当年だったらしく、いつもと違う雰囲気での開催でした。
それぞれの発表が終わったあとに、閉会のあいさつがありました。「今後も里町の文化の火を消してしまうことのないように…」と、言うような月並みのあいさつがありました。
僕が、その文化ってなんのことだろうか?何を以て文化と言っているのだろうか?と疑問を抱きながらあいさつを聞いていたあと、
会場にいた、あるおばあちゃんの声を聞き逃しませんでした。
「もう、火は消えてるよ。」
のひとことでした。
島の文化の火は消えている、ハッキリとした口調で、そんな風に言われました。良い意味でも、悪い意味でも、モヤモヤの残る時間になりました。
この島の文化とはなにか、改めて考える機会になりました。
2010年11月05日
32年のつきひ
以前「けんた興味あるかも」と手渡されていた昭和53年の甑島島勢振興調査報告書を読んでみた。
まず、タイトルが長くて読む前に心が折れそうで「ある」。
※報告書チックに(笑)
その報告書は、離島経済社会の展望や課題などが述べてあり、甑島における産業の現況や課題・将来への施策や展望・アンケート結果などがおよそ250ページにわたり論述的に書かれてている貴重なもの。
その中のアンケート結果で甑島の「漁業をともかく盛んにすべきだ」がおよそ70%に対して「農業には希望はない」が20%もある。しかも、現状でみると、農業については絶望的な評価しか与えられない。とまである
。
さすがにこれには、笑ってしまったよ。そんなに強く断言しないでおくれ(笑)もっとやさしい言い方あるでしょ!!
希望は、ありますから(笑)
近年になって、ようやく「第6次産業」や「半農半Х」という言葉や考え方は浸透しつつあるけれど、32年前のこの報告書内にもそれらに似たことが書いてあることに気が付いた。
以外掲載文―
「新しい産業も含めて、全産業を総合した仕組み(トータル・システム)を合理的に構成して立ち向かうほかないと思う。」
まさに、これは第6次産業のことではないだろうか。そして、
「半農半漁が、そのまま再現することはないが、農業はいぜんとしてトータル・システムの重要で欠くことのできない一部分。」
これが、半農半Х。
32年も前に、甑島農業の将来像をほんわりと且つ、的確に描いているひとたちがいたのだ。
「それなのに」それなのに、たったひとりの20代で「ある」(笑)。
甑島の農業に希望はない。
はたして、32年後はどうなっているのか一層楽しみになってきた。
GLOBAL KOSHIKI DESIGN + 山下商店の第6次産業とは、半農半Хとは…如何なるものか!(笑)
つづく
こころ折れなければ、
つづく
まず、タイトルが長くて読む前に心が折れそうで「ある」。
※報告書チックに(笑)
その報告書は、離島経済社会の展望や課題などが述べてあり、甑島における産業の現況や課題・将来への施策や展望・アンケート結果などがおよそ250ページにわたり論述的に書かれてている貴重なもの。
その中のアンケート結果で甑島の「漁業をともかく盛んにすべきだ」がおよそ70%に対して「農業には希望はない」が20%もある。しかも、現状でみると、農業については絶望的な評価しか与えられない。とまである
。
さすがにこれには、笑ってしまったよ。そんなに強く断言しないでおくれ(笑)もっとやさしい言い方あるでしょ!!
希望は、ありますから(笑)
近年になって、ようやく「第6次産業」や「半農半Х」という言葉や考え方は浸透しつつあるけれど、32年前のこの報告書内にもそれらに似たことが書いてあることに気が付いた。
以外掲載文―
「新しい産業も含めて、全産業を総合した仕組み(トータル・システム)を合理的に構成して立ち向かうほかないと思う。」
まさに、これは第6次産業のことではないだろうか。そして、
「半農半漁が、そのまま再現することはないが、農業はいぜんとしてトータル・システムの重要で欠くことのできない一部分。」
これが、半農半Х。
32年も前に、甑島農業の将来像をほんわりと且つ、的確に描いているひとたちがいたのだ。
「それなのに」それなのに、たったひとりの20代で「ある」(笑)。
甑島の農業に希望はない。
はたして、32年後はどうなっているのか一層楽しみになってきた。
GLOBAL KOSHIKI DESIGN + 山下商店の第6次産業とは、半農半Хとは…如何なるものか!(笑)
つづく
こころ折れなければ、
つづく
2010年10月31日
おみやげ改革

 一刻も早く甑島の「おみやげ改革」に取り組まなければならないと思っています。
一刻も早く甑島の「おみやげ改革」に取り組まなければならないと思っています。改革とは、大げさーー(笑)
甑島各港の売店やお土産物屋に並ぶクッキー・海産物などのほとんどが、島とは無関係のものばかり。本土の工場で製造し、パッケージに甑島の文字を印刷。もしくは、甑島シールを貼るのみ。
依然としてそれらの商品は存在しつづけているのだけれど、本当に、「選ばれて」いる商品なのだろうか?ではないとすれば、数ある一種の「ニセモノ」の中から消去法で手にしているのではないかと僕は思うのです。
これまで色んな土地を旅してきて、多くのニセモノ?に出会ってきました。そのたびに、ツーリストとして悲しくなったことをたびたび思い出します。
旅だけに(苦笑)
「結局、僕らツーリストは、低迷した地域経済をわずかに潤していくお金でしかないのかなぁ…」「地域の観光ってそんなものなのかな…」ってガッカリ。
その経験があるからこそ、僕はやっぱりMade in KOSHIKIにこだわりたいと思うし、買うことの先にある、何でもないような日常の風景を考えていたいと思うのです。
いま僕は、商品づくりだけでなく、商品を通じて変化していくであろう地域の未来の姿に想いを馳せています。そして、島内外を問わず、それを可能にしていく仲間たちと出会っていけると信じているのです。
みんなで同じ未来図を描くのは難しいです。だけど、自分自身がどう在りたいかは、誰にだって描いていけるはずです。
切り拓いていけるのです。
僕は、世界に通用する格好いい甑島人になりたいし、うらやみよりも誰かの憧れでありたい。
これは僕個人の欲望であり、たしかな原動力。甑島のおみやげ改革は、まだまだ始まったばかりですが、
…
とあるクレジット会社のコマーシャルでも言っています。「買い物は世界を変える」ってね(笑)
そのうち、うちの田んぼから石油がでるかもしれないな。
2010年10月30日
時計草の棚
 いよいよ甑島も寒くなり、上空にはシベリアからの渡り鳥である鶴の群れたちが列をなして飛び交っています。
いよいよ甑島も寒くなり、上空にはシベリアからの渡り鳥である鶴の群れたちが列をなして飛び交っています。そんな中、早くも夏の収穫期に向けて時計草(パッションフルーツ)の棚づくりをしました。
上甑町では、よく作られているパッションフルーツですが、これまで里町ではあまり見かけませんでした。
去年の夏、おそらく人生で初めてパッションフルーツを食べて、僕の百姓心に火がついたのが事の発端です。
KOSHIKI ART PROJECTのメンバーで、いつもヤマシタファーム(仮称)のサポートにきてくれるマユさんと、そのマユさんのお父さんが休日を返上して時計草の棚を作って下さいました。
途中、近くに住むノリおじさんも小さな耕運機を持って畑を耕してくれました。
道行くひとたちも何ができるのかと、不思議そーうに眺めていくのです。
家の棟上げのように餅投げをせんか!餅投げせんと、良かとができんどー、って近くの畑のおじさんが笑って過ぎてゆきました。
そんな風に?、島のみんなに見守られながら時計草たちは、すくすくと育っていくことでしょう。
これから、もう夏が楽しみです!
2010年10月19日
玄関先の贈りもの
 島に帰ってきて3ヶ月が過ぎた頃、2年ほど耕作を放棄していた土地を借りて、祖父と水田の再生に取り組みました。
島に帰ってきて3ヶ月が過ぎた頃、2年ほど耕作を放棄していた土地を借りて、祖父と水田の再生に取り組みました。ようやく1年が経ち、その水田でできた島米(ひのひかり)をこの秋、収穫することができたことを大変嬉しく思います。
また少し、この島の究極の百姓に(笑)近づけたでしょうか。
島米は、鳥害の影響などもあり、予定よりも少ない収穫でしたが約一週間の天日干しを終えて、確実に甘味が増してきました。
また、その最中にもスズメの大群がここぞとばかりにやってきたのには、いよいよ僕も呆れました(笑)
脱穀作業を終え、地主さんへの御礼参りにと、僕はその俵を担いで足早に向かいました。
「勉強になりました、ありがとうございました。」そういって、米俵を縁側に置いたのですが
要らない、
私はこのために、けんたくんに貸したんじゃないよと言って一向に受け取ろうとしてくれませんでした。
その次の日のお昼、
昼食時に帰ると、自宅の玄関には焼酎とビールが積んでありました。
地主さんからの贈り物でした。
僕は、言葉を失いました。
母への伝言は、
「島の為にって頑張る、けんたくんに呑ませて下さい。」とのこと。
一度も、その地主さんに島の為とか、なんだとか、僕は言った覚えなどなく、とても不思議な気持ちでした。
地主さんは、いつも僕のことを気にかけてくれていたんだな、心配していたんだなと、とても幸せな気持ちになった、そんなある日の出来事。
2010年10月10日
「島」帰る。
 初めて入った喫茶店で、偶然会った知り合いの女性に「俺、これから島に帰ります。」って云うと、
初めて入った喫茶店で、偶然会った知り合いの女性に「俺、これから島に帰ります。」って云うと、なんか…それ格好良いね、といわれて僕はドキッとした。
その女性にドキッとしたのではなくて、ちょっとドキッと(笑)
いやいや本当は、「島」っていうのが「格好良い」の対象になるってことにドキッとしたんです。
※ここ2つとも大事(笑)
一般的に島のイメージって、そんなに悪くないと思うんです。良いというよりも、憧れに似た感じなのかな?
言葉にすると、あったかいとか、スローライフとか、美味しいとか、自然がいっぱいとか、結構「やさしい感じ」のものになっていることが多い。
だから、そういう場所に住んでいる、帰る場所があること、ふるさとって素敵だね。そんな風に憧れる彼女の「格好良い」だったんだと思う。
これって、僕は、すっっげーーー大事なことだと思う。
そのイメージは、例えばテレビであったり、観光のパンフレットであったり、ラジオであったり新聞、雑誌。
時には、ヤマシタケンタという島のひとそのものが、地域のイメージになることもある。
観光で島を訪れるひとは「甑島」に対するそれらを期待してフェリーに乗るんだけど、そもそも、そのイメージ(情報)が間違っていたものだったり、装飾されたものだったとすれば、帰りのフェリーで得られる旅の満足感は小さいはず。
地域の情報発信って、いまはこんな時代だし、気軽にできちゃうんだけど、それなりの責任があるってことは忘れずにいたいと思うんです。
皆さんが抱く甑島ってどんなイメージなんだろうか。僕らの暮らしぶりを客観的にみて評価してくれる、我こそがよそ者だ!わたし…、実はよそ者なの。という方(言わない方)の意見を大募集したいと思います(笑)。
そういった、ニーズとシーズをすり合わせていく作業は、この島の誰がするのだろうって思うと、とても不安に思います。
地域を良くすることって
経済の発展だけじゃない。
島に生きる満足感、
島を訪れる満足感って
「甑島」とか「島」に対するイメージと、実体験を通して感じていく「そのひとにとっての本当の価値」が積み上がっていく信頼関係のことだと思う。
この先もずっと、「島」は僕らの帰る場所で在り続けることができるだろうか。
2010年10月06日
もう、やめろ。

 そう言われて、
そう言われて、本当にやめようかなって思った。
農業学校へ通ったわけでも、農業研修をうけたわけでもない僕には、誰から何を言われたとしてもつらかった。
この島に農業のプロはいない。
僕が島に帰って間もない頃、ある役場職員からいわれた言葉。僕は、正直腹が立った。この島では農業が確立していないことはわかっているけれど、それでも目の前で腰を曲げて土を耕しているおじいさんやおばあさんたちがいることは忘れたのだろうか。
なぜに無いものをねだるのか。
どこを見ているのか。目の前に素晴らしいひとたちが大勢いるというのに。
その時は、反抗する術も持ち合わせていなかったし、意見を言う気にもなれなかった。
ただ笑って、へへへって。
悔しかった。
一方的に提案と強制ばかりが繰り返される。なぜに、若者にして欲しいことばかりを願って、したいと言っていることをサポートする術を持ち合わせていないのだろうって。
いままで何人の若者たちが夢を諦めただろうか。島を離れていっただろうか。
僕は思う。
彼らは島を見捨てたのでもなく、逃げ出したのでもない。一度は帰ってきたふるさとに
それ以上、
とどまる理由が無かったのだ。
これからの島を考えるとき、その事実は決して無視されてはいけないはずだと僕は思う。
地域社会では、はじめから答えが決まっていることは多く、こうでなければならないという型も決まっている。
そういった状況の中で、社会的な弱者である若者たちが逃げ場もなく、本音など話せるわけもないのだ。ただでさえ少ない島の若者、以前とは比べものにならないほど一人ひとりの負担は大きくなっている。
若い奴らは人の言葉に耳を傾けないという。おそらく、僕もそう言われているひとりだけれど、
たぶんそれは違うと思った。
耳を傾けないのではなく、大人と呼ばれる人たちの言葉は、若者のためを思ったアドバイスのようにみえて、結局は自分を守るための一種の干渉にすぎないような気がする。
最近の若者は…
本当に耳を傾けないのは、一体誰なんだろうか。
いつも笑ってていいね、あんたは自分の好きなことして悩みなんかないでしょ?
僕は、ないと云った。
何一つない、と強がった。
ある、と言ったところでそれさえも羨ましがられるのだから、初めから話にならないのはわかっている。
やることが多くても、決して順風満帆とは言えない毎日を送っていて、いまの気持ちを繋ぎとめるものは何なのか、僕を島にとどまらせる理由は何なのかって考える。
跡継ぎでもない自分が島に帰ってきたこと。ここに家庭があるわけでもない。仕事があるわけでもない。
時間は一刻一刻と過ぎていく。
腰のヘルニアが痛む。
ひとりで靴下を履くのも、玄関で靴を履くのだって必死になってもがいてる。
僕はひとりでバカをみているのかもしれない。見ているとすれば、いつまでバカを続けるのだろうか。おそらく、長くは続けていられないことを自分が一番知っている。
なんと言われても構わないが、
この島にとどまる理由が無くなったとき、僕もこの島を離れるに違いない。
2010年10月03日
美味しくない島の米
 急遽、島米の収穫日からおよそ2ヶ月のあいだ「新米札」を付けることにしました。
急遽、島米の収穫日からおよそ2ヶ月のあいだ「新米札」を付けることにしました。特別な理由は無いんですが、お米の美味しい季節はやっぱり新米を食べて欲しいという単純な思いがあるから、ひらめいたのだと思います(笑)
昔から島の人たちは口を揃えて「早期米は始めのうちだけで、あとは美味くない」「初めのうちは、普通作と変わらないけど…」と言います。聞くひと、聞くひとそう言います。
次第にその言いぐさは「島の米は美味しくない」として語り継がれるようになっているような気がします。
残念なのは、そのひとたちのリアルな実感だけではなくて、何となく語り継がれているから、みんなも言っているから、自分もそう言っているような印象を受けることです。
確かに、お米の保存が難しいのは事実ですが、それは今のところ甑島に限ったことではなく世界共通です。(ロシアで凄い冷凍技術を開発中なのは除いて)
さらに、本当に美味しい時期は、収穫してから7日間だけという極端な方までいらっしゃいます。
僕は作り手であり、一消費者でもあるので、そういう環境や状況の中で自分自身や、島米そのものを客観的に見ようとする努力はしています。
しかしながら、ふるさとのお米が全体的に美味しくないと言われてしまうのはやはり辛いことです。
まるで、その人がそのひと自身を否定しているような、或いは甑島という地域を拒絶しているような感覚を僕は感じてしまい悲しくなるのです。
そんな中で誰が前向きな意見を口にしてくれたでしょうか。
新米を食べて、「島の新米は美味しいね。」を共有すればいいはずなのに、どこかの地域と比較したり、良いことは棚に上げてマイナスの部分ばかりを共有している。
なんだか、できないこと、ダメなこと、あきらめ、劣等を口にだして、皆が「そうだよね」と言ってくれるところに一種の安堵感があるような気がしてならないのです。
しかも、安堵したところで、気持ちが落ち着いたとしても現状は何も変わらないのです。
それは、お米だけでなく、地域社会の暮らしのあちこちでもよく見られることで、それぞれ不満を口にするだけで誰も本気で変えようとはしないのです。
シンプルだと思います。
もちろん容易ではないけれど。
何かを変えようとするとき、大きな対象を変えようとするから難しくなる。まずは自分がやってみる。一気にすべてを変えるのではなくて、少しずつ変わってみる。捉えかたや角度を変えてみること。そういう、小さなこと・見えにくいことの積み重ねが大事なんじゃないかって。
新米札が、それにあたるかは分からないけれど、きっとそういう思いがあったからなんだと思う。
2010年09月30日
小さな積み重ね
 注文をもらった。収穫した。新しい計量器を買った。車の修理代を払った。段ボールを仕入れた。商品を卸してもらった。
注文をもらった。収穫した。新しい計量器を買った。車の修理代を払った。段ボールを仕入れた。商品を卸してもらった。これは、去年の今頃には出来なかったことばかり。
最近は、大きな成功ばかりに目がいって、目の前にある小さな出来事、成功や達成してきてたことに気が付いていなかったような気がするなぁ…
自分のいただいたお金が何であるのか、なぜ僕の絵葉書やお米を選んで買ってくれたのか。自分できちんとそのことをわかっているのだろうか。
それがわかっていなければ、どんなに売り上げようと僕にとって意味はないと思う。
1ヶ月で800円しかなかった収入が、一年経って少しずつ増えてきた。目標には未だ届かないけれど、800円の重みは今でも時折感じている。
「その時は損したなぁって思うけど、あとでかえってくるよ。大事なのは、相手の気持ちになって愛を持つこと。大きなことなんかしなくていいの。積み重ねがあなたを大きくしてくれるんだから。」
島のひとの言葉に、何事も小さなことの連続と積み重ねであることを実感して、いまの自分を認めようと思った。
できたこと、できていないこと、できなかったこと。全ての自分と、全ての事実を受け入れようと思う。
まずは、そこから。
そうして受け入れたとき、自分が今、これから何をすべきか、本当にしなければいけないことが見えてくるような気がする。
僕は、選ばれるひとになりたい。選ばれる商品をつくりたいし、選ばれる生き方をしたい。選ばれるということ。それが、この島の未来であると信じているから。
だからこそ、選ばれる理由が何であるのかを提供する側として分かっていなければならないのだと思う。
全ては、小さな積み重ね。
甑島の玉石垣もひとつの石の集合体であるように、一歩一歩「実感」を踏みしめながら額に汗して進むこと。
完成図を描きながら自分の「小さな成功」を積み上げていきたいと、改めて思うのでした。そして、それが誰かの幸せでありたいと願うのでした。
よし、次は草払い機を買おう(笑)
2010年09月25日
力道山は、もういない。
僕は美空ひばりを知らない。
だけど、好きだ。
なんだか分からないけれど、空に架かる虹を見ていて幸せな気持ちになる、あの感じに近いのかな?
「虹」を別な言葉で表現すると、僕の中では、夢とか希望とか理想とか目標とか、勇気とか、たぶんそんな言葉になる。
戦後復興、高度経済成長期。
みんなの理想が「まだ」描けた時代に、彼女は悲しみを帯びた日本人の心を必然的に引き寄せた。
いまみたいに一家に二台も三台もテレビがある時代じゃない。街中をイヤホンしてそれぞれが自分のipodで歌を聞く時代じゃない。
白黒のテレビやラジオを取り囲み、それらが家族やまちの中心にあったからこそヒット曲やスターが生まれたんだと思う。
「みんな」で戦後の悲しみを共有し、支え合い、これからの日本を考える、感じる。そんな場所、そんな歌、そんな人たちがいた。
時代が移り変わり、社会が豊かになり、それぞれの価値観が多様化した。歌謡曲だけでなく、ヒップホップ、ジャズ、ロック、演歌など幅広い音楽が自由になり、それぞれがそれぞれのスタイルを楽しめるようになった。
気が付けば「美空ひばり」的な社会の中心や理想、みんなの夢や目標を抱くことが難しい時代になっていた。
それは、何かが崩れはじめたとかいうよりも「違う」ということが認められるようになったのだと思う。
だけど、それに歯止めが利かなくなったから豊かなのに成熟しない。たぶん、そんな感じだ。
―
島の将来像を描くこと、思いをひとつにすること、意識を共有すること。それは、かなり困難なことだと思う。
だけど、今を生きる者たちにとっては目を背けることはできないことだと思う。
俺、もっと真剣になれ。
美空ひばりは、もういない。
力道山も、もういない。
だけど、好きだ。
なんだか分からないけれど、空に架かる虹を見ていて幸せな気持ちになる、あの感じに近いのかな?
「虹」を別な言葉で表現すると、僕の中では、夢とか希望とか理想とか目標とか、勇気とか、たぶんそんな言葉になる。
戦後復興、高度経済成長期。
みんなの理想が「まだ」描けた時代に、彼女は悲しみを帯びた日本人の心を必然的に引き寄せた。
いまみたいに一家に二台も三台もテレビがある時代じゃない。街中をイヤホンしてそれぞれが自分のipodで歌を聞く時代じゃない。
白黒のテレビやラジオを取り囲み、それらが家族やまちの中心にあったからこそヒット曲やスターが生まれたんだと思う。
「みんな」で戦後の悲しみを共有し、支え合い、これからの日本を考える、感じる。そんな場所、そんな歌、そんな人たちがいた。
時代が移り変わり、社会が豊かになり、それぞれの価値観が多様化した。歌謡曲だけでなく、ヒップホップ、ジャズ、ロック、演歌など幅広い音楽が自由になり、それぞれがそれぞれのスタイルを楽しめるようになった。
気が付けば「美空ひばり」的な社会の中心や理想、みんなの夢や目標を抱くことが難しい時代になっていた。
それは、何かが崩れはじめたとかいうよりも「違う」ということが認められるようになったのだと思う。
だけど、それに歯止めが利かなくなったから豊かなのに成熟しない。たぶん、そんな感じだ。
―
島の将来像を描くこと、思いをひとつにすること、意識を共有すること。それは、かなり困難なことだと思う。
だけど、今を生きる者たちにとっては目を背けることはできないことだと思う。
俺、もっと真剣になれ。
美空ひばりは、もういない。
力道山も、もういない。
2010年09月24日
いつか来る日
 鹿児島・天文館でのTenBizの皆さんとのトークディスカッション「ダダモレ公開会議」を終えて、翌日は城山観光ホテルでのものづくり企業経営者塾に参加。そして、約一年ぶりの大阪にきた。
鹿児島・天文館でのTenBizの皆さんとのトークディスカッション「ダダモレ公開会議」を終えて、翌日は城山観光ホテルでのものづくり企業経営者塾に参加。そして、約一年ぶりの大阪にきた。近鉄百貨店の文化サロンにて甑島講座の講師。来春、九州新幹線が全線開通すると言うことで、それに合わせたPRキャンペーンの一環でした。はじめてのトークは、トラブル続きで多くのかたに迷惑を掛けてしまったと反省しています。
全ての問題は、自分の「準備」の甘さにあると思う。常に様々なリスクを想定しながら、最善を尽くすことが出来ていなかったような気がするなぁ。
なんて考えていると電話が鳴り、事後のパソコントラブルの報告。申し訳ない気持ちでへこんでいます。
後悔、先に立たず。
いい経験をさせていただきました。この機会を用意してくださった方々に感謝します。
―
つくづく想いを伝えることは難しいと思いました。
僕の言葉が、どれだけの方に届いたのか分からないけれど、こちらを見上げる視線から来場者の熱い気持ち・溢れ出すもの・こみ上げてくるものを僕自身は感じることができた。それは、何にも代え難い収穫でした。
それを無駄にしないために、自身の次のアクションを考えると、島のためにやるべきこと(求められていること)の輪郭が少しだけ見えてきたように思います。
そして、僕の考えていること、やっていることが自分ひとりの想いではなく、多くのひとたちの想いであったことに気付くことができたのは、これからの原動力であり、島に生きながらプロジェクトを継続していく勇気になるのだと思います。
島の外側にも多くの仲間がいること、島の内側にも仲間が増え続けていること。それは、互いの自信となり、ふるさとの誇りとなり、いつの日か甑島列島の地域力となる気がしています。
いつか訪れるその日のために、僕は、また今日から準備を進めようと思います。
2010年09月23日
あったかいもの
今日は、中秋の満月。
美しい月に見とれていると、甑島の静かな夜とやわらかな島風が恋しくなりました。
と、いうのも先週末より自分のしごとで鹿児島市内のあちこちを動き回っています。
明日からは、久しぶりの大阪でam5:30に起床予定(起きれるかは疑問)。近鉄百貨店の文化サロンにて特別講座とあっては、さすがに緊張しています。
準備が不十分なのは否めないですね。ただ、今頃になってそれを嘆いてもしかたないので、伝えたいことだけを自分自身の言葉で伝えようと思います。
鹿児島滞在中にKAGOSHIMA KAYAKSの代表である野元さんに云われたこと。「言い続けていくことが大切なんだよ。これだけの人がいるんだから、いつか誰かの心に止まるときがくる。」
僕は、なるべく僕自身の経験を通じて感じてきたリアルを常日頃から仲間に伝えていこうと思っています。ただし、人前で話すのは苦手なんです。
そんなことを言うと、皆ウソつけって顔をするけど…僕は、人と話しをするのが好きなんです。面白い話しを聞くのが好きなんです。だけども、一方的に投げ掛けることには慣れていないのです。
誰かの前に立って、何かを伝えるのはとても恐いことです。
自分の中にある、権威みたいなものに対するジレンマがあるのだと思います。偉いとか、強いとか、力とか。そういうものに対して、気が付くといつも恐怖心や反抗心を抱いています。
誰が(何を守ろうとして)決めたのか分からないような暗黙のルールや社会の常識が多すぎる気がします。
ひとはこうあるべきとか、こうでなければいけないとか、何の疑いもなく押し付けられるのは御免です。
そういう、いろんな物事の前提は、誰がいつ誰のために決めたのかって話し。
答えは、いつだってそのひとの中にしかないのです。それを奪うことなどできませんよね。
なら、何ができるのか?
甑島という、僕のふるさとを通じて、誰かの心に何かしら「あったかいもの」を残すこと。それが、僕の使命だと思っています。
島のPRをして観光客の数を増やすとか、島民の収入を増やすとか、僕の知ったことではないです。
それはあくまで、結果であり目的ではないと思っています。
学生時代に「ヤマシタの作品は、いつもあったかいんだよな。」ある教授から云われた言葉を思い出しました。なぜ、その時にあったかいと言われたのか今なら少しだけわかる気がします。
作品を直接レンジであたためたからではないことだけは確かですね(笑)
その理由を自分の言葉で伝えていくには、もう少し時間が掛かりそうです。だから、それをわかりたくて人前でお話する機会をいただきました。自分の気持ちや考え方を確かめる、そういう貴重な時間になりそうです。
あっ、am3:35。
貴重な睡眠時間が、あと2時間しか有りません(笑)
美しい月に見とれていると、甑島の静かな夜とやわらかな島風が恋しくなりました。
と、いうのも先週末より自分のしごとで鹿児島市内のあちこちを動き回っています。
明日からは、久しぶりの大阪でam5:30に起床予定(起きれるかは疑問)。近鉄百貨店の文化サロンにて特別講座とあっては、さすがに緊張しています。
準備が不十分なのは否めないですね。ただ、今頃になってそれを嘆いてもしかたないので、伝えたいことだけを自分自身の言葉で伝えようと思います。
鹿児島滞在中にKAGOSHIMA KAYAKSの代表である野元さんに云われたこと。「言い続けていくことが大切なんだよ。これだけの人がいるんだから、いつか誰かの心に止まるときがくる。」
僕は、なるべく僕自身の経験を通じて感じてきたリアルを常日頃から仲間に伝えていこうと思っています。ただし、人前で話すのは苦手なんです。
そんなことを言うと、皆ウソつけって顔をするけど…僕は、人と話しをするのが好きなんです。面白い話しを聞くのが好きなんです。だけども、一方的に投げ掛けることには慣れていないのです。
誰かの前に立って、何かを伝えるのはとても恐いことです。
自分の中にある、権威みたいなものに対するジレンマがあるのだと思います。偉いとか、強いとか、力とか。そういうものに対して、気が付くといつも恐怖心や反抗心を抱いています。
誰が(何を守ろうとして)決めたのか分からないような暗黙のルールや社会の常識が多すぎる気がします。
ひとはこうあるべきとか、こうでなければいけないとか、何の疑いもなく押し付けられるのは御免です。
そういう、いろんな物事の前提は、誰がいつ誰のために決めたのかって話し。
答えは、いつだってそのひとの中にしかないのです。それを奪うことなどできませんよね。
なら、何ができるのか?
甑島という、僕のふるさとを通じて、誰かの心に何かしら「あったかいもの」を残すこと。それが、僕の使命だと思っています。
島のPRをして観光客の数を増やすとか、島民の収入を増やすとか、僕の知ったことではないです。
それはあくまで、結果であり目的ではないと思っています。
学生時代に「ヤマシタの作品は、いつもあったかいんだよな。」ある教授から云われた言葉を思い出しました。なぜ、その時にあったかいと言われたのか今なら少しだけわかる気がします。
作品を直接レンジであたためたからではないことだけは確かですね(笑)
その理由を自分の言葉で伝えていくには、もう少し時間が掛かりそうです。だから、それをわかりたくて人前でお話する機会をいただきました。自分の気持ちや考え方を確かめる、そういう貴重な時間になりそうです。
あっ、am3:35。
貴重な睡眠時間が、あと2時間しか有りません(笑)
2010年09月19日
2010年09月17日
自分のしごと
 中学生の女の子が「けんた兄ちゃんの職業ってなんなの?」って聞いてきたそうだ。その子の親は、突然の質問と戸惑いで答えられなかったみたいで、
中学生の女の子が「けんた兄ちゃんの職業ってなんなの?」って聞いてきたそうだ。その子の親は、突然の質問と戸惑いで答えられなかったみたいで、後日、問い合わせがあり(笑)、僕の職業は探偵ですと答えると…さすがにその冗談には苦笑いされました。
島の中学生たちも気になっているという、僕のしごとは
甑島に仕事をつくる、しごと。
だなんて、島のひとからみたら笑っちゃうよね。自分ひとりさえも生計立てられてないのにさ(笑)格好つけんなってね。
だけど事実からは目をそらさずにいたい。どこにも属さずに約一年間続けてこれたということは、やっぱりこの島にとって意味のあることなんだと思う。
中学生たちが僕の職業を気になっているってことは、島の近い未来を担うこどもたちが、僕の働きを通じて「小さな変化」を感じてくれているんだと思う。
彼ら彼女たちは、高校がない甑島を離れて、いずれ親元を離れて暮らすようになる。世の中の15歳たちよりも一足早く社会と向き合うようになる島のこどもたちだ。
いつの日か、彼らが自分の夢を叶えるために「島に帰る」という選択肢があってもいいんじゃないか。夢を叶えるために東京へ行くことと同じように。
僕は、何と答えることができるのだろうか。
「島には仕事がない」「なにもない」「お金にならない」「若いひとがいない」
その答えを
今、僕は自分自身のリアルな経験を通じてわかろうとしているのかもしれないな。
あなたの仕事はなんですか?
2010年09月01日
no title
展覧会を終えてKOSHIKI ART PROJECT 2010に関わった作家・アシスタントスタッフたちが次々と島を離れていきます。
お世話になったスタッフや島のひとたちへの挨拶まできちんと済ませる者、作品の片付けもままならない作家、滞在した空き家を丁寧に掃除する者、そうでない者。これまでの7年間、200名を超える作家やスタッフそして、多くの島のひとたち大勢とアートプロジェクトを通じて関わってきました。
手放しでは喜べないプロジェクトの現実も含め、毎年、僕らが成長するために沢山の課題をいただいています。
そういう意味でも、やっぱり終わりではなく始まりなんだと思います。
その度にいつも思うのは、アートプロジェクトって、結局辿りつくのは誰かに向けられた心であり人間そのものだということ。
アートだとかなんだとかは、その行為の総称でしかないということ。
いま地元スタッフが、休みを返上して後片付けに追われています。この3ヶ月間、ほぼ毎日、朝から晩まで息つく暇もないくらい動き回ったメンバーたちに「有り難う」と伝えたいと思います。
僕は、事務局の人間でありながら展覧会の最終日からほとんど何もしていません。バスガイドを中断して消防団員として消火活動に走ったり、お世話になった作家やスタッフの見送りもろくにできず、朝から葬式の準備にあれこれ…島の国勢調査員に…と、
地域社会のド真ん中にいます。
これは僕だけのことではなく、ほかの地元スタッフも同様に。
それがこの地域で、「甑島で、つくる。」ことの大切さなんじゃないかって思っています。
どんなにお金を支払ってもこの島では、ことは動かないのです。
葬式の最中、裏方でそつなく動き回っている、親戚でも家族でもない地域のおばさんがたを見ながら、そんなことを考えていました。
地域とアート…
僕自身もわからないことが沢山あるからこそ、それをわかりたくて毎年、毎日、この夏を準備しているんだと思います。
Engawa Cafeのノートに記された、高校生たちの「いつか島に帰ってきます」の文字。
自分たちが、この島で頑張りたいと思える理由はそこにもあるんだと思います。仕事がいくらあっても、魅力のない島には誰も帰りたくないものです。
実際に、僕は仕事がなくても帰ってきたひとり。だからこそ、わかることもあるし、伝えられることもあります。
量とか数字とか、それも大切かもしれないけれど、後輩たちの感動やその言葉と素直な感情は、誰にも計ることなどできないのです。
アートプロジェクトは、人と人であり、地域もまた、人と人のあいだで起きているリアル。
人が輝けば、地域は輝く―
自分自身のリアルな実感を持って、そんな気がしています。
お世話になったスタッフや島のひとたちへの挨拶まできちんと済ませる者、作品の片付けもままならない作家、滞在した空き家を丁寧に掃除する者、そうでない者。これまでの7年間、200名を超える作家やスタッフそして、多くの島のひとたち大勢とアートプロジェクトを通じて関わってきました。
手放しでは喜べないプロジェクトの現実も含め、毎年、僕らが成長するために沢山の課題をいただいています。
そういう意味でも、やっぱり終わりではなく始まりなんだと思います。
その度にいつも思うのは、アートプロジェクトって、結局辿りつくのは誰かに向けられた心であり人間そのものだということ。
アートだとかなんだとかは、その行為の総称でしかないということ。
いま地元スタッフが、休みを返上して後片付けに追われています。この3ヶ月間、ほぼ毎日、朝から晩まで息つく暇もないくらい動き回ったメンバーたちに「有り難う」と伝えたいと思います。
僕は、事務局の人間でありながら展覧会の最終日からほとんど何もしていません。バスガイドを中断して消防団員として消火活動に走ったり、お世話になった作家やスタッフの見送りもろくにできず、朝から葬式の準備にあれこれ…島の国勢調査員に…と、
地域社会のド真ん中にいます。
これは僕だけのことではなく、ほかの地元スタッフも同様に。
それがこの地域で、「甑島で、つくる。」ことの大切さなんじゃないかって思っています。
どんなにお金を支払ってもこの島では、ことは動かないのです。
葬式の最中、裏方でそつなく動き回っている、親戚でも家族でもない地域のおばさんがたを見ながら、そんなことを考えていました。
地域とアート…
僕自身もわからないことが沢山あるからこそ、それをわかりたくて毎年、毎日、この夏を準備しているんだと思います。
Engawa Cafeのノートに記された、高校生たちの「いつか島に帰ってきます」の文字。
自分たちが、この島で頑張りたいと思える理由はそこにもあるんだと思います。仕事がいくらあっても、魅力のない島には誰も帰りたくないものです。
実際に、僕は仕事がなくても帰ってきたひとり。だからこそ、わかることもあるし、伝えられることもあります。
量とか数字とか、それも大切かもしれないけれど、後輩たちの感動やその言葉と素直な感情は、誰にも計ることなどできないのです。
アートプロジェクトは、人と人であり、地域もまた、人と人のあいだで起きているリアル。
人が輝けば、地域は輝く―
自分自身のリアルな実感を持って、そんな気がしています。



![[私はKOSHIKI ART PROJECTを応援します。]](http://img01.chesuto.jp/usr/koshikiart/koshiki-art-project-2009_blogparts_006.jpg)